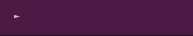日常の仏教語【相続】(そうぞく)
人が亡くなった時にその財産などを遺された人々が引き継ぐ「相続」。その分配のために集まって遺品を整理していると、懐かしい品が出てきて思い出話に花が咲くことがある一方で、トラブルのもとになってしまうことも。
この「相続」元々は仏教語で、この世にあるすべての物事(相)の原因と結果は連続し、途絶えることがないという意味
ローソクの火を例えに出せば、その火はずっと灯っているように見えますが、一瞬で燃えては消え、その熱を受け継いで新たな火が起こるということが非常に短い時間で繰り返されています。その繰り返しで一つの火として存在しているように見えるのです。
このように仏教では、あらゆる物事が原因と結果の連続性の中に存在していると考えます。時代とともに、この「受け継ぐ」という部分だけが注目され、現代のような意味になったとされます。
仏教では特に「心の相続」を重要視します。心に浮かんだことは一瞬で消えますが、それは後の私たちの感情や行動に影響を与えます。しかし、心を直接変えるのは容易ではありません。だからこそ、善い心を生み出すために善い行いを積み重ね、その心を相続することの大切さが仏教では説かれています。
相続というと”モノ”にばかり目が行きがちですが、言葉や生き様など亡き人が遺してくれるものは他にもたくさんあるはず。目に見える”モノ”の相続だけではなく、亡き人の想いや、生き方などの”心”の良い部分も相続し、自身の人生の糧としたいですね。 【浄土宗新聞2月号より】